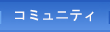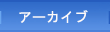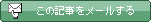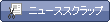ドアにノックの音がした。
「どうぞ」
祥一は机に向かい、本に目をやったまま応えた。
ドアを開けて入ってきたのは同じアパートに住んでいる伊吹健治だった。
「金さん、飯を食いに行きませんか」
すでに六時をすぎている。祥一もそろそろ飯に出ようかと思っていたところだった。
共同炊事場があるが、大半が外食だった。伊吹も祥一もほとんど外で食事を済ませていた。
「行こうか」
伊吹の誘いはちょうどよいところだった。
いい日和である。七月なかばで、まだ梅雨は終っていないのに、よく晴れてさわやかな風がゆるやかに吹いていた。散歩がてら食事に出るのにちょうどよかった。
伊吹が夕食に祥一を誘うのが日課のようになっていた。寂しいか、あるいは無聊(たいくつ)なのだろう。その点は祥一も同じだった。
一階と二階合せて八部屋ある簡易アパートで、兄妹二人で住んでいる者が二組いるから、住人はちょうど十人だが、このように気軽に食事に誘ったり、お互いの部屋を訪ね合ったりしているのは、一階のA号室に住んでいる伊吹か、でなければ隣室のF号室の岡田文夫ぐらいのものである。祥一の部屋はG号室だった。
岡田は例によって碁会所に行っているようだ。岡田も、伊吹も、そして祥一も、同じ国立のT大学の学生だが、岡田は碁に凝って留年二年目であり、いまだに二年生である。つまり、まだ教養学部の学生だが、経済学部を志望している。
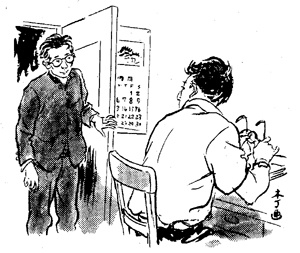 |
伊吹は法学部三年だが、この四月から大学に行っていない。祥一は工学部合成化学科三年で、彼もこの一年は留年することにしている。
三人とも留年を決め込んでいる、いわばアウトサイダーだった。留年の理由はそれぞれ異なっているが、アウトサ.イダーなりのよしみを無言のうちに感じ合っていた。
夏とはいえ、外に出ると、夕方の涼しい風が吹いていた。まだところどころに畑の見られる西荻窪の町外れである。道路を隔てたアパートのすぐ斜向かいは、すでに操業をやめている時計工場で、場内のあちこちに樹木が鬱蒼(うっそう)と茂り、雑草も伸び放題になっている。
「いい日だな」
と祥一はいった。
「うん」
そんなことには関心がないという様子で、伊吹は顔を少しうつ向けながら歩いていた。考えごとに耽(ふけ)っているのだろう。そういう伊吹にはもう慣れているので、祥一の方でも気にしない。
法学部の学生なのに、伊吹はいまドストエフスキーに熱中している。工学部の学生なのに、祥一も小説ばかり読んでいる。ついこのあいだ、祥一の部屋の本棚に、志賀直哉全集と太宰治全集が隣り合せに並んでいるのを見て、伊吹が怪訝(けげん)そうな顔をしたことがある。
「志賀直哉と、太宰治と、どういう関連性があるんですか」
「両方の気質が、ぼくの中にあるということだろう」
祥一はいったが、
「そういうこともあるんですかねえ」
と伊吹は不思議そうだった。
伊吹は二年生まで学生自治会の委員だった。三年に進級すると同時に自治会委員をやめ、大学に通うのもやめた。
木丁 画
1984年6月19日(火曜日) 4面掲載
1984年6月19日(火曜日) 4面掲載



 最終更新日: 2026-02-26 03:21:35
最終更新日: 2026-02-26 03:21:35