祥一は、虚脱した心で真っ直ぐ下宿に帰った。それは、虚脱感というより、むしろ苦痛に近かった。その頃、祥一は、こんなことを日記に書きつけている。
「九月十×日。暑りときどき雨。
地球から打ち上げたロケットが、はじめて月に到達した日。一昨日ソ連が打ち上げた月ロケットが、三十五時間後の今朝六時すぎ、月に到達したというニュース-アメリカかどこかの天文台からのニュースを、十分と経たぬうちに耳にできる-考えてみれば、ずいぶん驚異的な科学の発展である。科学は際限なく進歩して行く。しかし、人聞という生き物は旧態依然である。月にロケットが到達しても、人間は相変わらず苦しみ、悲しみ、寂しがり、そして泣く。相変わらず矛盾をはらんだままである。感情の生き物である。科学は、そんな人間の感情を滑稽に思いながら、ナンセンスだと突っぱねて、独走しているかのようだ。どこかで破綻しないだろうか?」
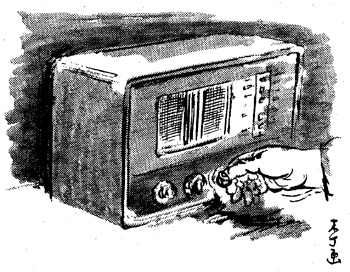 |
| |
「九月十×日。曇り。
いろいろなことを考えて、やりきれない心持に陥ることがしばしばある。いまでこそ、試験勉強にあくせくしていなければならないことを、ずいぶん苦痛に感じているけれども、しかし、考えてみれば、こうしていやが応でも勉強せざるをえないでいるときの方が、かえって救われているのではないか。試験から解放されたとき、またあの虚脱状態、空(うつ)うな気持にみまわれるのではないか。人生に対する例の漠然とした、寂しい不安に陥って、苦しい思いに胸を締めつけられるのではないか。そして、本を読む気にもなれず、街をさ迷い歩き、酔うことによってすべてを忘れようとする、あの生活がまた舞い戻ってくるのではないか」
そして、試験最終日の前日の日記には、こう記されている。
「九月二十×日。晴れ。
わけもなく胸が辛くてならぬ。蒼白な顔面と、カサカサに乾いた唇と、何ものをも感受しえぬ圧し潰(つぶ)されんばかりの脆弱(ぜいじゃく)な胸郭と、光も潤いもない空ろな眼(まなこ)。これは人聞ではない。廃物化した細胞の寄り集まりにすぎない。
明日の統計学の準備をいい加減なところで切り上げて、ウイスキーを飲み、十一時就床」
いま思えば、一種の神経衰弱に陥っていたのかも知れない。とにかく、彼はそんな心の状態で、二年前期の期末試験の最終日を迎えたのだった。
湯島の下宿に帰ると、彼は鞄を机の上に放り投げ、畳の上にごうりと横になった。試験から解放されたというのに、どうにも気が滅入ってならないのだが、それが何のせいなのか、彼にもわからない。
その日は朝のうちは雨催(あまもよ)いの曇り空だったが、昼近くになるにつれ、雲が薄くなり晴れ間もときどき顔をのぞかせるようになった。腕まくらをしながら、彼はしばらく窓の外の空に目をやっていた。階下で、家主の小学生の息子が、何やら騒いでいる声がきこえた。その声を打ち消そうとするかのように、彼はつと立ち上がって、机の上のラジオのスイッチを入れ、また腕まくらで畳に横になった。
小学校に通っているはずなのに、家主の息子はときどき学校を休む。今日も休んだのだろう。一人息子だけに、家主は、夫婦とも、息子が可愛くてならないらしかった。学校を休んでも、注意めいたことはいわないらしかった。
彼は、ラジオをきくともなくききつつ空に目をやっていた。曇り空に青間が次第にひろがって行くようだ。
1984年8月11日8面掲載

