「金と名乗るようになったのは大学に入ってからだ。ぼくも高校を出るまでは、森本という日本名を使っていた。敦賀の実家では、いまもその名字を通名として使っている」
祥一は答えた。
「どうして大学に入ってから本名を使うことにしたのかね」
伊吹は重ねてきいた。そういうことを率直に質問してくるところが、伊吹らしいところだった。普通の日本人は、そんな程度のことも、質問を憚(はばか)るものだ。引越してきた最初の日に、「朝鮮人ですか」とずばりときかれたとき、普通の日本人とは違う伊吹を感じたものだが、ここでも祥一は同様の感じを抱いた。
「通称名の使用は紛らわしいから、本名で通すようにって、大学当局からいわれたからさ」
焼鳥の煙の匂いの中で、祥一は、大学当局の係員にそういわれたときのことを思い返した。
あれは、入学式の数日後だったと思う。四十人ばかりのクラスの者一同が、何かの書類を受け取りに、構内の銀杏(いちょう)並木の傍らの、古びた木造の建物の中にある事務局に行った。何の書類だったか。履修課目届出用か何かの書類だったか。
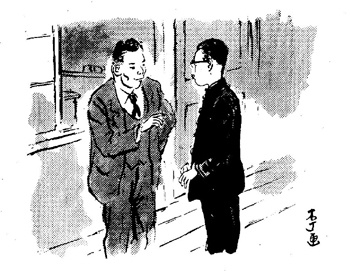 |
| |
ひとりひとり名を呼ばれ、窓口で紙袋入りの書類を受け取ったのだが、祥一が人々の面前で「金さん」と呼ばれたのは、そのときがはじめてだった。それまでずっと「森本」と呼ばれてきただけに、その名はすでに自分の骨の髄にまでしみ込んでいる感じなのに、不意に「金」と呼ばれ、彼は違和感と同時に当惑をおぼえた。いわば、無意識のうちにも隠し続けてきたものを、突然白日のもとにさらけ出されたような感じだった。高校三年のときの担任の先生は、彼のそんな気持を察しているかのように、ひそひそ声で「金」という名字を口にしたものである。
大学入試の受験願書と内申書を作成する段階になったある日の授業のあと、担任の数学の先生が、
「森本君、ちょっと」
と祥一を教室の外に呼んだ。
「受験願書と内申書を作らなくちゃならないんだけど、君の名前についてだがね」
先生の口調と態度には、廊下を往来している他の生徒の耳を憚っている気配が感じられた。
「君の戸籍名はどうなっているの?森本祥一なのか、金祥一なのか」
戸籍名とは、何のことだろう、と彼は一瞬とまどった。戸籍謄本など見たこともなかったからである。家の箪笥の抽出しに蔵(しま)つたままになっている、外国人登録証に記されている朝鮮名のことだろう、そう思って、彼は、
「金祥一です」
と答えた。
「願書も、内申書も、一応本名を書かなくちゃならないんでね。じゃあ金祥一という名前で作るからね。それから、卒業証書の名前もそれにするからね」
相変わらずあたりを憚っているふうに、低い声で先生はいった。それでいいね、と念を押しているような調子さえ祥一には感じられた。そして、祥一の方でも、「金」などという名字は使ったこともないけれど、願書や内申書は本名でなければならない、というのなら、その名を書かれても仕方がない、といった気持がしたものだった。
そうか、俺の本名は「金」だったっけ-彼はそのとき、ひさしく忘れていたものを思い出させられたような気がした。
1984年8月1日4面掲載

